◎プロローグ:コスパ重視の読書からの脱却
ここ数年、僕の読書は経済やビジネスに関する本が中心でした。もちろん面白いと感じる本もありましたが、その目的はあくまで「情報のインプット」。読書そのものを楽しむというよりは、常にアウトプットの手段や成果を意識し、自分の読書スピードや読解力に焦りを感じながらページをめくっていました。
しかし、J.G.フレイザーの超大作『金枝篇』を読み始めると、そんな実用主義的な読書観は、いきなり拒絶されます。
◎知識の迷宮へ:読み進まないのに楽しい『金枝篇』
本書の**「ハチの巣をつついたような博引傍証」**には、読み始めた途端、いきなり無力感に苛まれます。なかなかページが進まない。それなのに、すごく楽しいのです。
実は、人類学に特に強い興味があるわけではありません。なぜこの本を購入したのか、自分でも思い出せないほどです。書名自体は学生の頃から知っており、書店で岩波文庫の5冊セットを見かけて、手が出なかったことも覚えています。
若い頃の僕は、いったいこの本の何に興味を抱いていたのか?それこそが、今この本を読むことで解明したい一つの謎として浮かび上がってきました。
◎フレイザーが挑んだ二つの謎
『金枝篇』自体も、二つの大きな謎をめぐる書物です。
- 森の司祭はなぜ前任者を殺す必要があるのか?
- なぜ殺す前に「黄金の枝」を折りとる必要があるのか?
フレイザーは、ウェルギリウスの『アエネーイス』を題材として、J.M.W.ターナーが描いた絵画『金枝』から物語を始めます。ローマ神話の世界から、イタリアの湖畔の森で行われる残酷な掟へと、読者を巧みにいざなうのです。そして、なぜそのような掟が継承されてきたのかを、世界中の事例をもとに解明しようとします。
◎いきなりの「脱線読書」の快楽
その謎に迫る前に、僕の読書は早速「脱線」を始めました。
『金枝』のモノクロ画像は文庫本にも掲載されていますが、色彩のない図版に、物足りなさを感じました。画像を検索すると、エキゾチックな風景画が見つかります。儀式を行う人物も描かれてはいますが、画家の主眼はあくまでその景色です。
代表的なイギリスのロマン派画家ターナーの作品は、展覧会で目にした記憶があります。気になって手持ちの図録を漁り、「インヴェラレイ城の見えるファイン湾」(山梨県立美術館収蔵)や「嵐の近づく海景」「ヘレヴェーツリュウスから出向するユトレヒトティ64号」(東京富士美術館収蔵)などの作品を見つけ解説にまで目を通し始めました。
人気の高い印象派に影響を与えた画家として、その画風の変遷を追うのもまた面白いものです。
◎脱線はどこまで許されるのか?
気づけばターナーについて調べるだけで半日以上を費やしていました。ウェルギリウスや『アエネーイス』についても調べましたが、ここで書き始めると脱線が止まりません。完全に『金枝篇』本文を読むより時間を費やしている状況です。
会社勤めをしていた頃なら、この時間を「無駄」に感じ、この本を投げ出していたに違いありません。
しかし今は、読書が少しも進んでいないのに、充足感に満たされています。この時間の無駄遣いが、すごく贅沢に感じられるのです。
ただ少し困ったことに、ターナーの絵画を眺めていたら、突然ジョゼフ・コンラッドの小説が読みたくなってしまいました。さらに『アエネーイス』の上下巻まで「ポチって」しまった……。
さて、この「迷走する読書」の旅、脱線はどこまで許されるのでしょうか。

未読のコンラッド
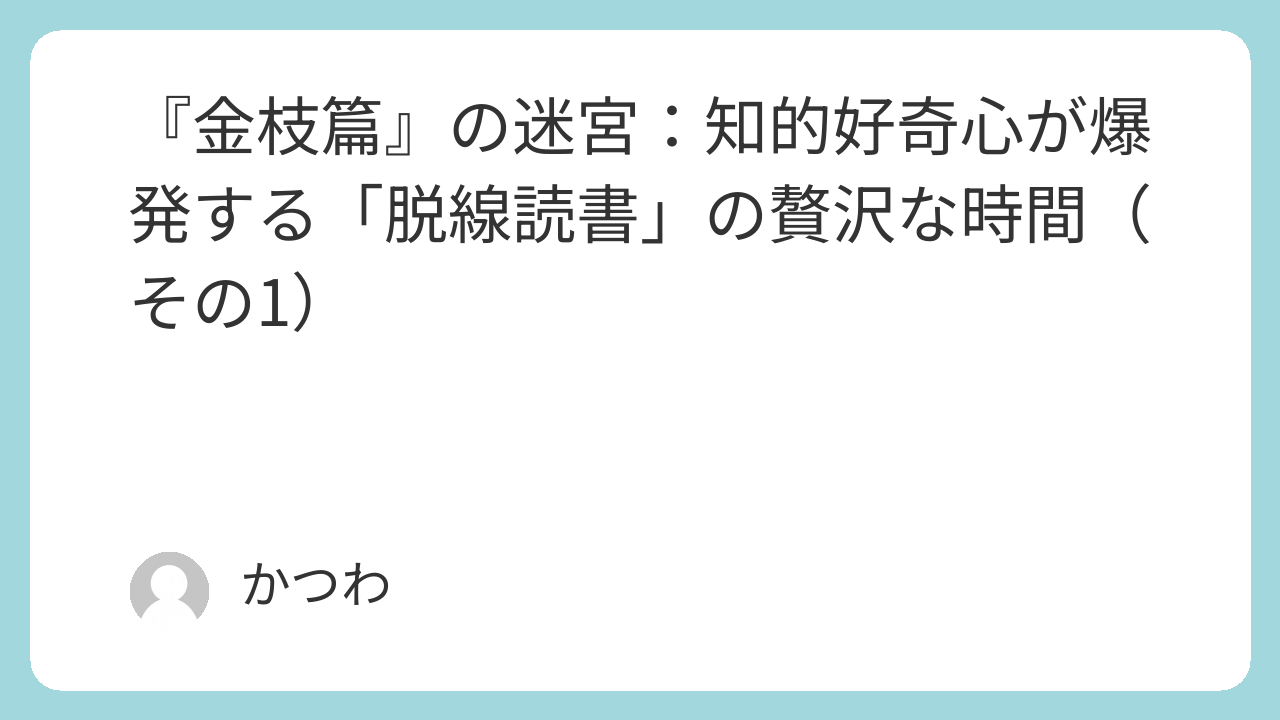


コメント